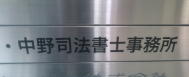

大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町一丁8番地4
三国ヶ丘ビル303号

R阪和線・南海高野線
三国ヶ丘駅

072-268-5044 |

※事務所までお越しになることが難しい場合はご希望の場所まで出張いたします。
主な業務エリア |

| 大阪府 大阪市・堺市・能勢町・豊能町・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・島本町・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町・松原市・羽曳野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市 兵庫県 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町・明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・姫路市・朝来市・篠山市・丹波市・その他 京都府 京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・南丹市・木津川市・大山崎町・久御山町・井手町・宇治田原町・笠置町・和束町・精華町・南山城村・京丹波町・その他 奈良県・滋賀県・和歌山県 上記以外の地域についてもご対応可能な場合がありますので、ご相談下さい。 |
 |
当ページは大阪で事務所を開設している司法書士が作成しております。
相続は人生において何度も経験するものではありません。したがって、そのような状況に直面したとき、相続手続きってどのようにすればいいのだろうか?とお悩み方々も多いのではないでしょうか。
当ページでは、相続手続きのなかでも比較的関わりのある方が多く、司法書士の専門業務でもある相続登記についてご案内しています。相続登記について疑問をお持ちの方々に少しでもご利用いただけましたら幸いです。
 |
不動産の所有者が亡くなられて相続が発生したときに、その不動産の名義を変えたいときには、登記所で所有者の名義を変更する手続きを行います。
登記所とは不動産登記記録(不動産の権利内容が記載された記録のこと)を管理している国の機関です。
 |
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることとなりました。猶予期間を過ぎても正当な理由なく義務に違反した場合にはペナルティ(10万円以下の過料)が科される可能性があります。
また、相続登記をそのまま放置していた場合に起こりうる問題として、登記記録上の所有者(名義人)だけでなく、その相続人も亡くなると、次の相続が発生し、その相続人も亡くなると、さらに相続が発生するというようなことになります。そのように何代もの相続が発生していたりすると、結果的に相続関係者が多くなるため、権利関係が複雑になってしまいます。
そして、不動産を売りたいときや不動産を担保にお金を借りたいときには、やはりその前提として相続登記をして、所有者名義を現在の所有者に変更する必要があります。
すると、もし家を売りたいと考え、いざ相続登記をする必要にせまられたときに、すでに相続が複数回発生していた場合には、あまり面識もないような親族同士が共同で相続人になっていることもあり、その方と連絡をとったり話し合いをしたりするのにもかなりの時間がかかってしまう恐れがありますし、話がまとまらないといった事態におちいってしまうことにもなりかねません。
したがって、このように困った状況を避けるためにも、可能であれば早めに相続登記手続きをされることをお奨めいたします。
 |
ある方が亡くなった場合に、いったい誰が相続人になるのかといった疑問もあると思いますので、ここでは相続人についてご説明いたします。
・亡くなった方に子がいれば子が第1順位の相続人になります。子は先に亡くなっているが、その子の子(孫)がいるときは孫が相続します(もし、孫も先に亡くなっており、その孫に子がいればその方が相続人になります。以下、同じ)。・子や孫などがおらず、亡くなった方の父や母がいれば、その方が第2順位の相続人になります(父も母も両方とも先に亡くなっているが、祖父や祖母が生きている場合は祖父や祖母が相続人になります)。
・父や母(祖父や祖母)もいなければ、第3順位で兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹も先に亡くなっているが、その兄弟姉妹の子(甥や姪)がいるときは甥や姪が相続します。なお、甥や姪も先に亡くなっているときには、それ以下の世代に相続することはありません。
・亡くなった方に配偶者(夫または妻のこと)がいるときは、配偶者は上記の方々とともに共同相続人になります。(配偶者の他に相続人がいないときは配偶者が単独で相続人になります。)
 |
公正証書遺言の場合には、遺言書があるかどうかを公証役場で調べてもらうことができます。
- 遺言書
- 亡くなった方の死亡を証明する戸籍謄本等
- 不動産を相続する方の戸籍謄本等
- 亡くなった方の住民票等
- 不動産を相続する方の住民票等
- 固定資産評価証明書等
→遺言書がある場合の相続登記手続きの流れ
 |
その話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産分割は相続人全員が合意しないといけません。
例えば、ABCの3名が相続人である場合に、3人による話し合いで「相続財産のうち甲土地と乙建物についてはAが相続し、丙土地についてはBが相続する」といったように決めます。このような遺産分割協議で決めた結果のとおりに相続登記を行う方法です。この方法が最も良く行われています。
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付)
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 亡くなった方の住民票等
- 不動産を相続する方の住民票等
- 固定資産評価証明書等
→遺産分割協議による場合の相続登記手続きの流れ
 |
- 子と配偶者が相続人になるときは、子と配偶者の相続分は2分の1ずつとなる。また、子が複数いる場合にそれぞれの子の相続分は2分の1をさらに頭数で等分した割合となります。
- 配偶者と直系尊属が相続人になるときは、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1になる。この場合も、父と母の両方が相続人であれば、3分の1を2分の1ずつした6分の1ずつとなります。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときは、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1になる。同様に、兄弟姉妹が複数いる場合にそれぞれの相続分は4分の1をさらに頭数で等分した割合となります。
- 兄弟姉妹が相続人になる場合で、被相続人(亡くなった者)と片方の親が違うときは、両親とも親が同じである兄弟姉妹の2分の1となります。
このように、法定相続どおりとするのであれば上記のような割合で相続登記を行うことになります。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 亡くなった方の住民票等
- 相続人全員の住民票等
- 固定資産評価証明書等
→法定相続分のとおりにする場合の相続登記手続きの流れ
※なお、上記の相続登記の必要書類は、ケースによって他にも書類が必要になる場合もございますのでご了承下さい。
「相続手続きの流れ」のページへ
当事務所への相続登記手続きのご相談やご依頼は、下記までお
気軽にご連絡下さい。 |
 |
 |
- 丁寧な対応を心掛けています。
- ご質問には、ご納得いただけるよう出来る限り分かりやすくご説明いたします。
- ご依頼頂いた業務は速やかに執り行います。
このページの一番上まで戻る



